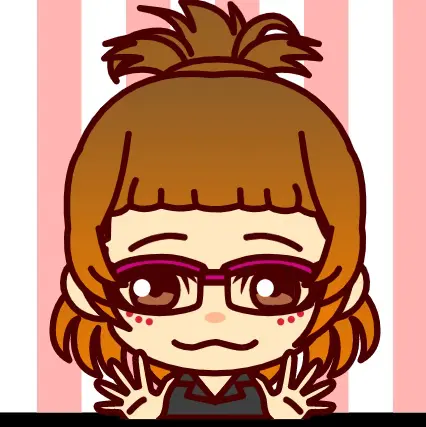 松下ひよこ
松下ひよこ三姉妹を育てています、看護師ママです。
自己紹介はコチラ
「ママ、保育園行きたくない…」
朝の支度中に泣きながら訴えられると、親としては心が痛みます。
「でも、仕事があるし、そう簡単に休ませるわけにもいかない…」
保育園の行き渋りは、どの子にも起こる可能性があります。でも、その理由は年齢によってさまざま。成長とともに変化する子どもの気持ちに寄り添いながら、適切な対応をすることが大切です。
今回の記事では、 保育園の行き渋りの原因や、年齢別の対応方法 を紹介します。我が家の体験談も交えてお伝えするので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
行き渋りとは


「行き渋り」とは、子どもが保育園や学校などに行きたがらず、嫌がることを指します。
主な理由は、大きく分けて4つ。
✔ 環境の変化への不安(新しいクラス・先生・お友達に慣れない)
✔ 親と離れることへの寂しさや不安感(特に低年齢ほど「ママ・パパがいい」となる)
✔ 園でのストレス(お友達とのトラブルや、苦手な活動がある)
✔ 体調や気分の問題(疲れや睡眠不足、なんとなく行きたくない気分)
年齢が低いほど「ママと離れたくない!」という理由が多く、成長とともに「園での出来事」が影響してくることが特徴です。
行き渋りが続くと、親も「このままで大丈夫?」と不安になりますが、 成長過程のひとつなので、適切に対応すれば落ち着いてくる ことがほとんど。年齢に応じた対応で、子どもを安心させてあげましょう。
保育園の行き渋り|年齢別対応方法


子どもの成長段階によって、行き渋りの原因や対応策は変わります。
ここでは 2歳~5歳の年齢別の行き渋り対策 を紹介します。
2歳児の対応
2歳は自己主張が強くなる「イヤイヤ期」の真っ最中。「保育園に行きたくない!」と泣いたり、玄関で踏ん張ったりするのも珍しくありません。
イヤイヤしている姿は「かわいい!」と思えるときもありますが、状況によっては「かんべんしてよ・・・」と思うことも。イヤイヤ期の対応は根気が必要ですよね。
対応のポイント
✔ 気持ちを受け止める:「保育園イヤなんだね」「ママも一緒にいたいな」
✔ 登園前のルーティンを作る:「この絵本を読んだら行こうね!」
✔ 先生と連携する:お迎え時に「今日はどんな様子でしたか?」と聞く
この時期は 「ママと離れるのが寂しい」 が大きな理由なので、 安心感を与えながら、ルーティンで切り替えられるように していくのがポイントです。
3歳児の対応
3歳は、自立心が育つが、不安も感じやすい時期です。会話が上手になり「保育園行きたくない理由」を伝えられる子も出てきます。新しい環境や先生に戸惑ったり、お友達とのトラブルが影響することも。
対応のポイント
✔ 理由を聞いてみる:「どうして行きたくないの?」と優しく質問
✔ 成功体験を作る:「昨日も頑張ったね!先生とおままごとして楽しかったね」
✔ 楽しみを用意する:「帰りに好きなおやつ食べよう!」「公園に寄ってみようか」
少しずつ「自分で頑張る」気持ちを育てながら、安心材料を増やしていくのがコツ です。
4歳児の対応
4歳は、集団生活が本格化し、お友達との関係が大きな影響を与える時期です。 「〇〇ちゃんと遊びたくない」「先生が怖い」 など、具体的な理由で行き渋ることが増えてきます。
対応のポイント
✔ 話をじっくり聞く:「誰かとケンカしちゃった?」
✔ 不安を和らげる言葉がけ:「先生に相談してみる?」「困ったときは〇〇ちゃんに助けてもらおう」
✔ 自己肯定感を高める:「あなたは頑張れる子だよ」
子どもが悩みを打ち明けられる環境を作りながら、前向きな気持ちに導いてあげましょう。
5歳児の対応
5歳児は、責任感が芽生えつつも、不安も抱える時期です。また、「小学校を意識し始める」時期でもあります。
先生やお友達との関係、役割へのプレッシャー から行き渋ることも。
対応のポイント
✔ 不安を一緒に整理する:「何がイヤなのか、教えてくれる?」
✔ 具体的な解決策を考える:「先生に相談しようか」「ママが見送りのとき手を振るよ」
✔ 達成感を感じさせる:「今日も頑張ったね!」
「自分で乗り越えられた!」という経験が、 小学校に向けての自信につながる ようにサポートしていきましょう。
我が家の行き渋り体験談!


うちの長女も保育園のときに、行き渋りをすることがありました。
保育園の行き始めや転園のとき、年度の始まりや長期休みの後は特に行き渋ることが多かったです。行き渋るときは、毎朝「ママがいい~!」「保育園行きたくない!」と号泣。パパが送っていくときは特に大変でした。
本人に行きたくない理由を聞いても、小さいうちは「行きたくない」の一点張り。
そこで、病院での経験を活用しようと思いました。入院してくる子どもは不安や淋しさを抱え、最初は泣いていることが多いです。しかし、病院の生活はある意味集団生活なので、食事の時間やテレビを見ていい時間、ベッドで過ごす時間、回診の時間、寝る時間などある程度決まっていました。
このルーティンに慣れてくると、先の見通しが立つので子どもも安心するようです。
そのため、朝起きてから保育園に行くまでの流れを決めるようにしました。
- 起きる
- 朝ご飯を食べる
- 歯みがきをする
- 着替える
- 保育園の準備
- 好きなテレビを見る
- 終わったら出発!
我が家ではこのように朝の流れを決め、 毎朝同じルーティンで支度する ことで、少しずつスムーズになりました。
また、「明日はお休みだから、今日はがんばろうね!」「今日は早くお仕事が終わるから、早く迎えに行けるよ」などの予定も伝えておくと安心するようでした。
今振り返ると、 子どもも保育園に行くための心の準備が必要だったのではないかと思います。朝の支度をルーティン化することで、保育園へ行く気持ちを整える時間にもなったのだと感じました。
保育園に慣れてきたり行くのが楽しいと感じるようになったりすると、行き渋りは少なくなって、「早く行こうよー」と言うようになりましたよ!
まとめ
保育園の行き渋りは誰もが経験する、育児あるあるだと思います。「うちの子だけじゃない」と思うだけでも、少し気持ちがラクになりますよ。
年齢によって行き渋りの理由は違うので、その子に合わせた対応が必要です。
行き渋りは成長過程のひとつと考え、気持ちを受け止めてあげましょう。親子で安心して登園できるよう、ルーティンや楽しみを作るのもいいですね。
子どもが安心して登園できるように、 焦らず、寄り添いながら乗り越えていきましょう!





